サブシステムの特性その後 ― 2008年02月11日

書斎用サブシステムへのLINN LK140導入後、一ヶ月ほど立ちました。実は次男が入試中のため、メインシステムで大きな音も出せないこともあって、ほとんどサブシステムで聞いていて、調整も大いに進みました。スペクトルアナライザーPAA3はもちろんあるのですが、はじめから測定に頼るのもどうかな、とか(妙にマニアックに)思いはじめ、とにかく耳で追い込んでいきました。で、本日、LK140導入後、はじめて測定して見ました。
んー、なかなか耳も正確なものです。400Hzに若干の凹み、サブウーハーのつながりにややギャップがあって、微調整しましたが、基本的にはほぼ素直な特性。微調整後のスペクトルが写真です。微調整によってやはり良い方向に変わりました。残念ながら、時には機械のお世話になるのも早道ですかねえ。200Hz付近のピークはたぶん部屋の問題でしょう。特性では目立ちますが、聴くとあまり感じません。どちらにしても7バンドではこんな細かいところは直せませんし。
現状で、最大のネックは、装置よりは部屋の性能。LK140のおかげで音量をあげてもひずみが感じられなくなりましたが、あまりあげると、今度は部屋の各部で共振が! 多少の天井補強で若干改善しましたが、完全に直すのは金がかかりそうなのであきらめます。ま、サブシステムでは静かに聴けということでしょう。すこしおとなし目の音であれば、相当に楽しめます。
んー、なかなか耳も正確なものです。400Hzに若干の凹み、サブウーハーのつながりにややギャップがあって、微調整しましたが、基本的にはほぼ素直な特性。微調整後のスペクトルが写真です。微調整によってやはり良い方向に変わりました。残念ながら、時には機械のお世話になるのも早道ですかねえ。200Hz付近のピークはたぶん部屋の問題でしょう。特性では目立ちますが、聴くとあまり感じません。どちらにしても7バンドではこんな細かいところは直せませんし。
現状で、最大のネックは、装置よりは部屋の性能。LK140のおかげで音量をあげてもひずみが感じられなくなりましたが、あまりあげると、今度は部屋の各部で共振が! 多少の天井補強で若干改善しましたが、完全に直すのは金がかかりそうなのであきらめます。ま、サブシステムでは静かに聴けということでしょう。すこしおとなし目の音であれば、相当に楽しめます。
オーディオとマッサージチェア ― 2008年02月03日

書斎用サブシステム用にマッサージチェアを買いました。TSR-03という安いものですが、ゴルフ場で試用してみたところ、機能はこれで十分。それより、私が気に入ったのは、通常はリビング用チェアとして十分に使えるすわり心地をめざしたという点。マッサージチェアって、普通は、リビングチェア代わりに使えるものではないですよね。その点でこのTSR製は、オーディオ観賞用リクライニングチェアとして十分使えそうでしたので、買ってみました。見た目もレザー風で高級です。
ただし、一点、もくろみ違い。マッサージしながら音楽を聴こうなんて思っておりましたが、ブンブンとモーターの音が大きいし、体を揺さぶられながらでは落ち着いて聴けませんねえ。とくに私のように音楽と対峙して聞くタイプには無理。
しかし、同じ姿勢で長く聴いていると疲れてくるので、そこで5分ほどマッサージして疲労回復し、また聴く、という使い方が、最高なのを発見。これで何時間でも聞いていられますよ。
そんなわけで、オーディオとマッサージチェアは相性がよろしい、というのが結論。もっとも、毎日こんなことをしていたらメタボになりそうです。
ただし、一点、もくろみ違い。マッサージしながら音楽を聴こうなんて思っておりましたが、ブンブンとモーターの音が大きいし、体を揺さぶられながらでは落ち着いて聴けませんねえ。とくに私のように音楽と対峙して聞くタイプには無理。
しかし、同じ姿勢で長く聴いていると疲れてくるので、そこで5分ほどマッサージして疲労回復し、また聴く、という使い方が、最高なのを発見。これで何時間でも聞いていられますよ。
そんなわけで、オーディオとマッサージチェアは相性がよろしい、というのが結論。もっとも、毎日こんなことをしていたらメタボになりそうです。
メンデルスゾーン ピアノトリオ ユリア・フィッシャー盤 ― 2008年01月31日

メンデルスゾーン ピアノトリオ No.1 & 2
Vn: Julia Fischer, Piano: Jonathan Gilad, Cello: Daniel Muller-Schott, Pentatone PTC5186 085
新進女流バイオリニスト、ユリア・フィッシャーと若手2名によるメンデルスゾーンのトリオソナタ。2006年のDSD録音で、SACDハイブリッド版です。私はそのCD面を聞いているわけですが、大変滑らかで美しく録音されています。この曲は他の録音版を持っていないので、このCDが最高なのかどうかはわかりませんが、私としては非常に気に入っています。ここ一年では私の最愛版です。とても気にいったので、他のユリア・フィッシャーのディスクも買ってみたのですが、残念ながらどれも愛聴版にはなりませんでした。よーく聴いて見ると、フィッシャーには悪いですが、このアルバムで特によいのはGiladのピアノのような気がしてきます。非常に繊細です。
実は、私のCDシステムも、このCDを基準に選んだようなものなのです。幸いにもSACDハイブリッド版なので、CDプレーヤーとSACDプレーヤーを混ぜて試聴することもできました。で、CD専用であるオラクルCDドライブ+CHORD-DAC64が勝利を収めたというわけなのですが。
オーディオ的には、3つの楽器が交互に出てくるので、スピーカーとかプレーヤーの音質チェックには便利といえます。左にバイオリン、中央にピアノ、右にチェロという配置が正しいはずですが、すこしでもバランスが狂っていると、ぐっとどちらかに寄ってしまうという面白い特徴があります。なんでかわかりませんが・・・。だからバランス調整にも非常に敏感。ついでに言うと、オラクル購入時の試聴で使ったJBL4338が聞かせたチェロのすばらしい音は、実は、いまだ私の4344では再現できていません。
使用DAC: CHORD DAC-64 Mk2
Vn: Julia Fischer, Piano: Jonathan Gilad, Cello: Daniel Muller-Schott, Pentatone PTC5186 085
新進女流バイオリニスト、ユリア・フィッシャーと若手2名によるメンデルスゾーンのトリオソナタ。2006年のDSD録音で、SACDハイブリッド版です。私はそのCD面を聞いているわけですが、大変滑らかで美しく録音されています。この曲は他の録音版を持っていないので、このCDが最高なのかどうかはわかりませんが、私としては非常に気に入っています。ここ一年では私の最愛版です。とても気にいったので、他のユリア・フィッシャーのディスクも買ってみたのですが、残念ながらどれも愛聴版にはなりませんでした。よーく聴いて見ると、フィッシャーには悪いですが、このアルバムで特によいのはGiladのピアノのような気がしてきます。非常に繊細です。
実は、私のCDシステムも、このCDを基準に選んだようなものなのです。幸いにもSACDハイブリッド版なので、CDプレーヤーとSACDプレーヤーを混ぜて試聴することもできました。で、CD専用であるオラクルCDドライブ+CHORD-DAC64が勝利を収めたというわけなのですが。
オーディオ的には、3つの楽器が交互に出てくるので、スピーカーとかプレーヤーの音質チェックには便利といえます。左にバイオリン、中央にピアノ、右にチェロという配置が正しいはずですが、すこしでもバランスが狂っていると、ぐっとどちらかに寄ってしまうという面白い特徴があります。なんでかわかりませんが・・・。だからバランス調整にも非常に敏感。ついでに言うと、オラクル購入時の試聴で使ったJBL4338が聞かせたチェロのすばらしい音は、実は、いまだ私の4344では再現できていません。
使用DAC: CHORD DAC-64 Mk2
デ・ワールト&アーメリングのペールギュント ― 2008年01月22日

グリーグ ペールギュント
エド・デ・ワールト指揮 サンフランシスコ響
ソプラノ:エリー・アーメリング
私の愛聴するペールギュントは、LP版時代からこれです。CDで買いなおしましたが、音の傾向は同じでした。1980年代のデジタル録音ですが、今聞いても非常に耳触りのよいきれいな音で録られていて、私がもっとも聞く回数の多いCDの一つになっています。低音の響きも不要な誇張もなく、非常に自然な響きです。で、なんといってもアーメリングが歌うソルベイグがいいのです。自信を持って推薦できるディスクの一つ。
面白いことに、このディスクは(珍しいのですが)声楽部分もDAC64で疑問なく聞けます。No.36SLのほうがLPで聞いた声には近いようにも思いますが、でも、DAC64のほうがきれいな声に聞こえます。不思議ですね。
使用DAC: CHORD DAC64 Mk2
エド・デ・ワールト指揮 サンフランシスコ響
ソプラノ:エリー・アーメリング
私の愛聴するペールギュントは、LP版時代からこれです。CDで買いなおしましたが、音の傾向は同じでした。1980年代のデジタル録音ですが、今聞いても非常に耳触りのよいきれいな音で録られていて、私がもっとも聞く回数の多いCDの一つになっています。低音の響きも不要な誇張もなく、非常に自然な響きです。で、なんといってもアーメリングが歌うソルベイグがいいのです。自信を持って推薦できるディスクの一つ。
面白いことに、このディスクは(珍しいのですが)声楽部分もDAC64で疑問なく聞けます。No.36SLのほうがLPで聞いた声には近いようにも思いますが、でも、DAC64のほうがきれいな声に聞こえます。不思議ですね。
使用DAC: CHORD DAC64 Mk2
メニューインのパガニーニVn協奏曲1,2番 ― 2008年01月14日

バイオリンの名手、パガニーニは4つのバイオリン協奏曲を残しています。その1,2番の名演とされるのが、バイオリン・メニューイン、エレーデ指揮、ロイヤルフィル。これも録音は古く、1960年。もちろんLPレコードで持っていたのですが、いまだそれを超える演奏に出会いません。録音でいえば最近、新進の女流、ヒラリー・ハーンの1番が出て話題でした。買ってみましたが、正直なところ、好きになれません。ま、録音クオリティは上がりましたけれど・・・。そんなわけで、メニューイン版のCD発売はないのか、と探したところ見つけてしまいました。写真はLPジャケットとCD版。単に演奏技術を誇示するのでなくて、じつにさりげなく弾いて、パガニーニの難曲から豊かな音楽性を引き出しているメニューインの技術に感心してしまいます。ワルターでもご紹介したデッカの名録音に比べれば、同時期ながらややレンジが狭いと感じるものの、現代のオーディオで演奏してもなんら問題ありません。本当は3番が好きなのですが、なかなかCDが見当たりませんね。
使用DAC: CHORD DAC64-Mk2、LPはオルトフォンMC*30。LPも盤状態が非常によいので、両者は優劣付け難いです。
使用DAC: CHORD DAC64-Mk2、LPはオルトフォンMC*30。LPも盤状態が非常によいので、両者は優劣付け難いです。
LINNパワーアンプがくれた初夢 ― 2008年01月10日

今日は、オーディオシステム更新の話題。といって、メインシステムでなく、書斎用のサブシステムのほうです。サブの構成は、http://www.asahi-net.or.jp/~rt6k-okn/audio/report/JBL4304/subsys1.htm
をご覧ください。レシーバーのR-K801が備える7素子イコライザー機能やトーンコントロールの機能が重宝してますが、さすがにパワーには限界があって、大音量でちょっと高域がひずみっぽくなってしまうのです。そこで昨年末に思いついたのが、R-K801のSP出力をプリ出力に転用してパワーアンプを繋ぐという反則技。R-K801のSP出力を22オームで受け、1/10に減衰してプリ出力とする回路を自作しました。出力段の負担が減るので、かなり低ひずみで出力されるはず。強力バッファ搭載のプリと思えばよいのです。
パワーアンプは、中古市場を探っていたら、運よく(か、運悪くかはわかりませんが)、LINN LK-140 ( 8オーム負荷で95W)なんていう理想的なものを見つけてしまいました。新品同様で、8万円。これは掘り出し物です。10年ほど前には、ステレオサウンドのベストバイ1位を数年続けた名器です。
しかし、いくらLINNが優秀でも、こんな反則接続で音がよくなるのかな~、無駄な投資かも、と実は怪しみながら、鳴らしてみました。すると、例のひずみっぽさは完全に解消。それどころか、イコライザのチューニングを少々変えるうち、これは大変な改造をしてしまったらしいことに気がつきました。高域が画期的に美しくなりました。これはLINNの音なのでしょうか。
あまり大音量で聞かない限りですが、曲によっては、4344のメインシステムより良いかもしれない、とか思う瞬間があるほどなのです。たった7Kgの銀の小箱が予想もしなかった夢のような音をプレゼントしてくれました。しばらくはメインシステムの電源を入れるのが面倒になりそうです。
詳細は、調整完了後に、オーディオページにレポートしたいと思います。
をご覧ください。レシーバーのR-K801が備える7素子イコライザー機能やトーンコントロールの機能が重宝してますが、さすがにパワーには限界があって、大音量でちょっと高域がひずみっぽくなってしまうのです。そこで昨年末に思いついたのが、R-K801のSP出力をプリ出力に転用してパワーアンプを繋ぐという反則技。R-K801のSP出力を22オームで受け、1/10に減衰してプリ出力とする回路を自作しました。出力段の負担が減るので、かなり低ひずみで出力されるはず。強力バッファ搭載のプリと思えばよいのです。
パワーアンプは、中古市場を探っていたら、運よく(か、運悪くかはわかりませんが)、LINN LK-140 ( 8オーム負荷で95W)なんていう理想的なものを見つけてしまいました。新品同様で、8万円。これは掘り出し物です。10年ほど前には、ステレオサウンドのベストバイ1位を数年続けた名器です。
しかし、いくらLINNが優秀でも、こんな反則接続で音がよくなるのかな~、無駄な投資かも、と実は怪しみながら、鳴らしてみました。すると、例のひずみっぽさは完全に解消。それどころか、イコライザのチューニングを少々変えるうち、これは大変な改造をしてしまったらしいことに気がつきました。高域が画期的に美しくなりました。これはLINNの音なのでしょうか。
あまり大音量で聞かない限りですが、曲によっては、4344のメインシステムより良いかもしれない、とか思う瞬間があるほどなのです。たった7Kgの銀の小箱が予想もしなかった夢のような音をプレゼントしてくれました。しばらくはメインシステムの電源を入れるのが面倒になりそうです。
詳細は、調整完了後に、オーディオページにレポートしたいと思います。
懐かしいMoogによる電子音楽 ― 2008年01月06日

ジ アメージング ニュー エレクトロニック ポップ サウンド オブ ジャン ジャック ペリー (キングレコード)
The Amazing New Electronic Pop Sound of Jean Jacques Perrey (Vanguard)
Moog(モーグ)とは、1960年代に現れた電子楽器。それを駆使して作曲、演奏をしたのがジャン・ジャック・ペリー。ディズニーランドのエレクトリカル・パレードのテーマの作曲者といえば、どんな曲か想像していただけるでしょう。1968年に、当時大流行した4chステレオテープでヴァンガードから発売されたソースが、2000年に、キングレコードからCDで発売。4chテープ(写真、当時で6000円もした)は、いまも大事に持っていますが、すでに再生可能な機材がありません。懐かしく思っていたので、再発売を知って速攻で買いました。
2chになってしまっても、その音楽としての魅力は変わらず。普段はクラシックしか聞かない私ですが、これは楽しい。まさに「これが電子音楽です」という曲と演奏。いまの電子楽器とちがって、どうやって音を作ったかがわかりそうなところも面白い。あれ、こんな音を楽器にしてる、見たいな感じ。そういえば、当時の4chテープの邦題は「脅威の電子音楽」だった。
この種のポップスは、絶対にパイオニアD-07aでなければ聞けません。マークレビンソンNo.36SLが完敗する非常に面白い例です。
使用DAC:パイオニア D-07a
The Amazing New Electronic Pop Sound of Jean Jacques Perrey (Vanguard)
Moog(モーグ)とは、1960年代に現れた電子楽器。それを駆使して作曲、演奏をしたのがジャン・ジャック・ペリー。ディズニーランドのエレクトリカル・パレードのテーマの作曲者といえば、どんな曲か想像していただけるでしょう。1968年に、当時大流行した4chステレオテープでヴァンガードから発売されたソースが、2000年に、キングレコードからCDで発売。4chテープ(写真、当時で6000円もした)は、いまも大事に持っていますが、すでに再生可能な機材がありません。懐かしく思っていたので、再発売を知って速攻で買いました。
2chになってしまっても、その音楽としての魅力は変わらず。普段はクラシックしか聞かない私ですが、これは楽しい。まさに「これが電子音楽です」という曲と演奏。いまの電子楽器とちがって、どうやって音を作ったかがわかりそうなところも面白い。あれ、こんな音を楽器にしてる、見たいな感じ。そういえば、当時の4chテープの邦題は「脅威の電子音楽」だった。
この種のポップスは、絶対にパイオニアD-07aでなければ聞けません。マークレビンソンNo.36SLが完敗する非常に面白い例です。
使用DAC:パイオニア D-07a
ワルターのベートーベン第8番 ― 2008年01月06日
ベートーベン 交響曲第8番、CBS SONY
ブルーノ・ワルター指揮、コロンビア交響楽団
ステレオ録音が発明された直後、1958年の録音です。引退していたワルターを呼び戻して、ステレオで取り直したという話です。名盤としてなんどもCD発売されていますけれど、私のはかなり初期のCD。本日聞きなおして、また感動しました。
そんな古い録音のは音が悪いに決まっているとお考えなら、ぜひ試しに一度聞いて欲しいのです。曲間や曲の静かなところで、わずかにテープヒス(ノイズ)が聞こえますが、そんなことをわすれてしまうほど、デッカの優秀録音はすばらしいです。私は機材の試聴にはこのCDを必ず持っていきます。ある意味、演出されて作られた音だと思いますが、すごい臨場感。弦を弾く音なんか、すごいリアルに聞こえます。楽器ごとにマイクが設置されているのかと思うほど。この音がよいと思える方は、きっと私と価値観が近い方だと思います。
使用DAC: CHORD DAC-64 MK-2
ブルーノ・ワルター指揮、コロンビア交響楽団
ステレオ録音が発明された直後、1958年の録音です。引退していたワルターを呼び戻して、ステレオで取り直したという話です。名盤としてなんどもCD発売されていますけれど、私のはかなり初期のCD。本日聞きなおして、また感動しました。
そんな古い録音のは音が悪いに決まっているとお考えなら、ぜひ試しに一度聞いて欲しいのです。曲間や曲の静かなところで、わずかにテープヒス(ノイズ)が聞こえますが、そんなことをわすれてしまうほど、デッカの優秀録音はすばらしいです。私は機材の試聴にはこのCDを必ず持っていきます。ある意味、演出されて作られた音だと思いますが、すごい臨場感。弦を弾く音なんか、すごいリアルに聞こえます。楽器ごとにマイクが設置されているのかと思うほど。この音がよいと思える方は、きっと私と価値観が近い方だと思います。
使用DAC: CHORD DAC-64 MK-2
カルミニョーラのヴィヴァルディー ― 2008年01月04日

ヴィヴァルディ 弦楽と通奏低音のための協奏曲
Vn: ジュリアーノ・カルミニョーラ
ヴェニスバロックオーケストラ
ARCHIV UCA-1065
ヴィヴァルディーと言えばイ・ムジチかと思っていた頭の古い私め・・・。このCDでは、こういう演奏もあったかと眼を覚ましました。カルミニョーラのバイオリンも絶妙ですが、オケの低音の響かせ方が従来のバロックの録音とはかなり違い、強烈です。ベースがブンブンきます。はじめはちょっと驚くけど、それはそれで非常に痛快。題名も、「通奏低音のための協奏曲」ってくらいですからこれで良いではないの(^^;
低音に隠れず、チェンバロなんかの高音もきれいに聞こえ、弦の響きも美しくかつソフトで、録音も非常に優秀。推薦できるCDの一つです。DAC-64が威力を発揮する例でもあります。
使用DAC: CHORD DAC-64 Mk-2
Vn: ジュリアーノ・カルミニョーラ
ヴェニスバロックオーケストラ
ARCHIV UCA-1065
ヴィヴァルディーと言えばイ・ムジチかと思っていた頭の古い私め・・・。このCDでは、こういう演奏もあったかと眼を覚ましました。カルミニョーラのバイオリンも絶妙ですが、オケの低音の響かせ方が従来のバロックの録音とはかなり違い、強烈です。ベースがブンブンきます。はじめはちょっと驚くけど、それはそれで非常に痛快。題名も、「通奏低音のための協奏曲」ってくらいですからこれで良いではないの(^^;
低音に隠れず、チェンバロなんかの高音もきれいに聞こえ、弦の響きも美しくかつソフトで、録音も非常に優秀。推薦できるCDの一つです。DAC-64が威力を発揮する例でもあります。
使用DAC: CHORD DAC-64 Mk-2
ツァラトウストラはかく語りき(マゼール版) ― 2008年01月03日

私の大好きな曲の一つが、リヒアルト・シュトラウスの「ツアラトウストラはかく語りき」。映画「2001年宇宙の旅」で使われたカラヤン版以後、いろいろと聞きましたが、ここでご紹介するロリン・マゼール指揮、ウイーンフィル版 (グラモフォン、UCCG5059)が、現在のところ、私の最高点。
昨年の「レコード芸術」誌の特集で、
「マゼール版は多くの方にとってノーチェックだろうが、ブランドテストをすればおそらく過半数がこれを選ぶのではないか」
というようなことが書かれていました。
「ほんまかいな?」と思って、買ってみましたら、録音・演奏ともこれは確かに最高のでき。 単にオーディオ的にみた音質だけでなく、演奏も、これまで愛聴していたメーター版をはるかに超えています。
使用DAC: マークレビンソンNo.36SL
昨年の「レコード芸術」誌の特集で、
「マゼール版は多くの方にとってノーチェックだろうが、ブランドテストをすればおそらく過半数がこれを選ぶのではないか」
というようなことが書かれていました。
「ほんまかいな?」と思って、買ってみましたら、録音・演奏ともこれは確かに最高のでき。 単にオーディオ的にみた音質だけでなく、演奏も、これまで愛聴していたメーター版をはるかに超えています。
使用DAC: マークレビンソンNo.36SL
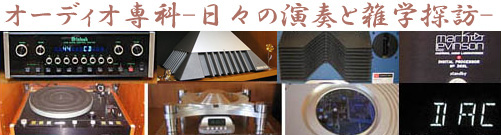
最近のコメント